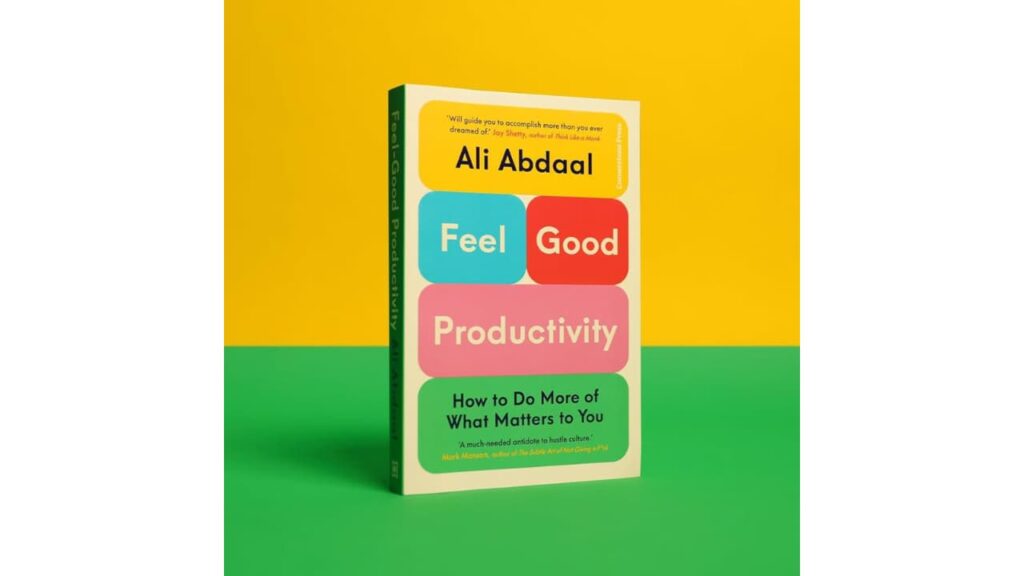今日は,YoutuberのAli Abdaalという方が書かれた「Feel Good Productivity」という洋書を紹介します。
難しい文法も多くなく,優しい文章で書かれていますので,英語中級者の方におすすめできる一冊です。何より内容が大変面白い。
英語の勉強も兼ねてYoutube動画を観まくっているのですが,本書の読みやすさに反して、リスニングは超ハードです。シャドーイングなんてできたもんじゃねえレベルで話すのが超絶速いので、リスニングは上級者向けかもしれません。
速度落として聴くのもアリ(Ali)ですね。
さて,本題に戻ります。
この「Feel Good Productivity」という本の内容を一言で表すと,「気分が良くなること(=Feel Goodになること)が,生産性(=Productivity)を上げる」ということです。
「生産性を上げる」と聞くと”Discipline!”,”Stoic!”みたいなイメージを抱く人もいるかもしれませんが,この本は逆です。
むしろ,「辛い・しんどいことじゃなくて,もっとFeel Goodになることを優先しようぜ!」という内容です。
Feel Goodになると、私たちにエネルギーが生まれ,生産性が上がる。だからFeel Goodになる。
”生産性”という話になると,
- 「食事も体調も時間もちゃんと管理して,休みなくバリバリ働け!」
- 「規律をもって,自分に厳しく,自分を追い込め!」
- 「血のにじむような努力をしろ!」
こういった“No Pain, No Gain”的な考えになりがちですが,むしろ逆かもしれないんだよということです。
少年ジャンプみたく,”たゆまぬ努力によって逆転するヒーロー”は物語でよく描かれますし,このような考え方になることはある意味仕方のないことですが。
そもそも,”生産性とは何ぞや”といった生産性そのものに対して疑問視する人たちもいて,一言で”生産性”といっても,色々な切り口で議論できる訳ですが,ここでは一旦置いておきましょう。
今日の記事はあくまで,「生産性を上げたいんや!」と必死になって,むしろ”Feel Bad”な方向に向かって迷い込んでしまっている人向けに,「ちょっと一回考え直してみないか?」と待ったをかける一冊として,本書を紹介しようと思います。
Aliは本書だけでなく自身のYoutubeで「努力は必ずしも苦痛である必要はない」という話をよくしています。
“True productivity is not dicipline, it’s joy.”(本当の生産性とは,規律(=自分を律して行動すること)ではなく,”楽しむこと”である)ということです。(”Hard work doesn’t have to be painful.”とかも言っています)
生産性を追い求める過程で,必ずしも辛酸を舐めるような苦しい思いをする必要はないんですね。
本書では,「じゃあどうすればFeel Goodになるねん!」という疑問に対しても,色々なヒントを書いてくれています。
本書は100近い論文が参考文献として引用されており,Feel Goodになる上で役立つ科学的根拠に基づいた考え方がたくさん書かれています。
ここで全ては紹介しきれませんが,本書のPart1で紹介されている「Energiser(エネルジャイザー)を見極めよう」という話だけ、すこーし紹介します。
Energiserとは,私たちにエネルギーを与えてくれるもの,ポジティブな感情をもたらしてくれるものを指します。
English Tidbits
Energy(エネルギー):名詞形
→Energise(エネルギーを与える):動詞形(他動詞でenergise yourselfなどと使う)。
→Energiser(エネルギーを与えるもの):名詞形
本書では,Energiserとして以下の”3つのP”が紹介されています。
①Play(遊び):その活動に遊び(心)を取り入れる
②Power(力):物事をコントロールする力,自信を手に入れる
③People(人):互いにエネルギーを与え合える仲間と過ごす
1つ目の「Play(遊び)」については,生産性とは程遠い存在のように聞こえるかもしれませんが,実はそうでもなく,本書ではノーベル物理学賞を受賞したリチャード・ファインマン博士(1918-1988)の逸話とともに解説されています。
さらに,「遊び」を日々の生活に取り入れる最初の一歩として「自分の遊びの性格タイプを選ぶ」ことが紹介されています。
性格を”選ぶ”とは何かというと,例えばアクションRPG等のゲームでは,「剣士で物理攻撃でザクザク切って戦いたい」とか,「魔法を駆使してクールに戦いたい」とか,「モンスターを操って,器用に戦いたい」とかありますよね。
それぞれ長所・短所がある中で、自分にとって「こういうタイプが好き」と感じるものを選ぶように,現実でも同じようにやってみようぜということです。
本書では,8つの性格タイプが紹介されており、「自分はどのタイプかなぁ…」とキャラ選び感覚で考えながら読んでいました。
ブログでは、著作権の関係であまり内容を紹介できませんので,気になる方はぜひ手に取って読んでみてほしく思います。(出版社から許可が出たら、Youtubeで紹介する予定です)
最後まで読んで頂きありがとうございました。